おすすめの弓道・アーチェリー教材
弓道射法八節習得プログラム〜射法八節を習得して中・貫・久を鍛え試合に勝つ方法〜【天皇杯覇者 土佐正明 監修】
弓道上達革命 〜初心者と指導者向け〜【天皇杯覇者 教士七段 増渕敦人監修】DVD2枚組
弓道上達の極意〜的中率アップの練習法〜【筑波大学体育会弓道部部長 松尾牧則 監修】
アーチェリー上達革命〜試合でも良い点数を打てるようになる効率的練習法〜【元・慶應義塾大学 洋弓部監督 佐藤達也 監修】DVD2枚組
【弓道とアーチェリーを掛け持ちしている選手もいる】

大まかな目安ですが、現在の
- 弓道の競技人口が14万人を超えている
のに対し、
- アーチェリーの競技人口は約1万2000人程度
だと言われています。
アーチェリーの競技人口は、ざっくり弓道の10分の1以下だということになりますね。
しかし、弓道の選手のなかには、アーチェリーを掛け持ちで行っている選手も少なからず存在します。
道具の種類が違うとはいえ、どちらも「弓と矢」を使って行うスポーツですから、確かに両方を掛け持ちするのはそれほど不自然ではないでしょう。
両方の競技に共通する動きやコツもあるため、弓道とアーチェリーを掛け持ちすることが、プラスに働く可能性も充分に考えられます。
ところが、弓道とアーチェリーを同時に行うことが、いいことづくめだとは言えません。
何らかの事情があって掛け持ちするのは構いませんが、「両方ともやったら2倍上手くなりそう!」なんて安易な考えで掛け持ちを始めるのは早計だと言えます。
そこで今回は、弓道とアーチェリーを掛け持ちすることで発生する、メリットとデメリットの両面を徹底的に検証していきたいと思います。
【そもそも弓道とアーチェリーの違いとは?】
弓道だけをやってきた選手、またはアーチェリーだけをやってきた選手のために、まずは
- 「弓道とアーチェリーの違いって何?」
という、根本的な部分からご説明しておきましょう。
両方を掛け持ちしてみたいと考えている方なら、早いうちに弓道とアーチェリーの違いを理解しておきましょう。
弓道とアーチェリーの見かけ上
- もっとも大きな違いは、使っている「弓」の違い
です。
- 竹などで作られたシンプルな「和弓」を使っているのが弓道
- 専用の補助具の使用が認められている近代的な「洋弓」を使うのがアーチェリー
です。
日本に古来から伝わる和弓に対し、洋弓は時代に合わせて進化を遂げてきたため、ハッキリ言って弓の性能そのものは洋弓のほうが上です。
そのため、弓道に比べるとアーチェリーのほうが的中率にシビアです。
- 弓道で最もメジャーな「的中制」は、矢が的に中ってさえいれば、どこに刺さっていても構いません
- アーチェリーは的の中心に近いほど評価が高くなる「点数制」が基本
です。
- 伝統的な弓を使って「自らの技術で矢を射る」ことに重きを置いたのが弓道
- 最新の道具を使って「正確に矢を射る」ことに重きを置いたのがアーチェリー
だともいえるでしょう。
その他、ルールやマナーといった大きな部分にも、数多くの違いが見られます。
実際に弓道とアーチェリーの両方を体験してみれば、この2つが「全く違うスポーツ」であることに驚かれるのではないでしょうか。
数多くの相違点を踏まえれば、「弓道経験がある人はアーチェリーもすぐ上手くなれる」とは一概に言えないということが分かることでしょう。
弓道とアーチェリーの違いを「アメフトとラグビー」「スピードスケートとフィギュアスケート」の違いに例える方が居ますが、まさに言いえて妙です。
【弓道からアーチェリーに転向するメリットとデメリット】
結論から言ってしまえば、弓道からアーチェリーに転向するメリットは、それほど多くありません。
もちろん、アーチェリーから弓道に転向するという場合でもまた然りです。
強いて言うならば、アーチェリーの方が競技人口が少ない分「ライバルが少ない」というメリットはあるかもしれません。
地方の大会なら、エントリー人数自体が少ないので、大会に入賞したり代表に選出される可能性は高くなるでしょう。
しかし競技人口が少ないということは「指導者に巡り合いにくい」「ライバルと切磋琢磨して成長できない」というデメリットも含んでいるため、手放しに喜べるメリットとは言えませんね。
デメリットとしては、「両方の競技に悪癖がつく可能性が高い」というのが大きいです。
実は弓道とアーチェリーでは使う筋肉も動きのコツも全く違うので、両方を平行して進めていると、どうしても齟齬が生じてしまうものなのです。
例えば
- 弓道で「引き直し」は認められていません
- アーチェリーでは時間内の引き直しが何度でも許可されています。
弓道専門の選手が引き直しなんて、初歩的なミスを犯すことはほとんどありませんが、アーチェリーと同時に練習している選手が、ウッカリ引き直してしまうというケースは珍しくありません。
他にも、アーチェリーに和弓独特の「押す動き」を入れてしまったせいで、記録が伸びなかったり、和弓をアーチェリー風の短い引き尺で引いてしまって、矢が飛ばなかったり…
それぞれのポイントがごっちゃになってしまうので、完全に転向しても慣れるまでには、かなり時間がかかってしまうでしょう。
弓道から転向してきた選手よりも、運動経験のないアーチェリー初心者のほうが、良い記録を出すなんてこともザラにあるくらいです。
もしも弓道からアーチェリーに転向するのであれば、弓道経験を「有利」だとは考えないことです。
これから始めるのは全く違うスポーツなのだということを胸に刻んで、新たな挑戦を楽しんでください。
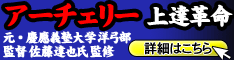
アーチェリー上達革命〜試合でも良い点数を打てるようになる効率的練習法〜【元・慶應義塾大学 洋弓部監督 佐藤達也 監修】DVD2枚組
関連ページ
- アーチェリーにも「射法八節」がある!?射形について
- 全日本アーチェリー連盟は、アーチェリーにおいて一本の矢を放つまでの一連の動作を8つに分解することを推奨しています。矢を放つまでの動作を8つに分解する…と聞いて、弓道の「射法八節」を思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。実際、アーチェリーの一連の動作は弓道の射法八節とソックリなんです。そこで今回は、アーチェリーの射法八節ともいえる8つのプロセスを簡単に解説していこうと思います。
- アーチェリーで記録を上げるために「視力」は必要不可欠なのか?
- アーチェリーの的は少なくとも18メートル、長ければ70メートルは先に設置されています。サイトやスタビライザーを使うとはいえ、これほど遠方にある的を狙うためには最低限の「視力」が必要になるでしょう。しかし実際のところ、アーチェリーはむしろ「視力が低くてもできるスポーツ」だといえます。アーチェリーで記録を伸ばすために必要なのは、的をしっかりと見据える視力ではなく、スタビライザーやサイトを上手く使いこなして視力を補う「感覚」です。
- アーチェリーの構えアンカリング・ホールディング・エイミングを理解しよう
- 日本で一般的な射法で、スタンス・セット・ノッキング・セットアップ・ドローイング・フルドロー・リリース・フォロースルーの8段階に分割されます。さらに的中率を上げたいならドローイングとフルドローの間に「アンカリング・ホールディング・エイミング」の3つの動作が隠されていることも知っておかなければなりません。そこで今回は、初心者が中級者に上がるために欠かせない「アンカリング・ホールディング・エイミング」の解説をしていきたいと思います。この3種の動作をしっかり理解して、アーチャーとしてひとつ上の段階にレベルアップしていきましょう。