おすすめの弓道・アーチェリー教材
弓道射法八節習得プログラム〜射法八節を習得して中・貫・久を鍛え試合に勝つ方法〜【天皇杯覇者 土佐正明 監修】
弓道上達革命 〜初心者と指導者向け〜【天皇杯覇者 教士七段 増渕敦人監修】DVD2枚組
弓道上達の極意〜的中率アップの練習法〜【筑波大学体育会弓道部部長 松尾牧則 監修】
アーチェリー上達革命〜試合でも良い点数を打てるようになる効率的練習法〜【元・慶應義塾大学 洋弓部監督 佐藤達也 監修】DVD2枚組
【アーチェリーの射法は弓道の「射法八節」によく似ている】

矢を放つまでの動作を8つに分解する…と聞いて、弓道の「射法八節」を思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。
実際、アーチェリーの一連の動作は、弓道の射法八節とソックリなんです。
アーチェリーの動きが、弓道の射法八節に似ているのは決して偶然ではなく、アーチェリーが日本人にも馴染みやすいよう、わざと似せられたものです。
その証拠に、
- アーチェリーの動作を8つに分解するという考え方を持っているのは、世界中でも日本だけ
であり、他の国では各々が打ちやすいスタイルで、自由にやって良いことになっています。
アメリカやヨーロッパではアーチェリーを「ハンティングスポーツ」として扱うことが多いため、海外のアーチャーは日本人のように、丁寧な射法を守ったりはしません。
そのため国際大会などでは、全日本アーチェリー連盟が指定する射法を守る必要は無いのですが、日本独特の射法をなぞることにはちゃんとメリットもあります。
大きなメリットとしては、
- 「初心者でも動きの基本が掴みやすい」
- 「弓道から転向してきた選手に馴染みやすい」
- 「大まかなコツを理解しやすい」
…などが考えられますね。
最初からある程度自由にやるのも悪くはありませんが、基礎を固める意味でも、アーチェリーの射法は学んでおいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、アーチェリーの射法八節ともいえる、8つのプロセスを簡単に解説していこうと思います。
アーチェリー歴の浅い初心者の皆さんは、以下の8つを覚えて的中率の向上に役立ててみてください。
【1.スタンス】
最初に行うのは「スタンス」と呼ばれる動作。
弓道の射法八節においては「足踏み」に相当するプロセスです。
シューティングラインを中心にして、両足のつま先が的の中心と一直線になるように直立してください。
このとき、足と足の間隔を自分の肩幅と同じくらいの広さにしておくと、重心が安定しやすくなります。
足は、ほとんど平行にしておくのが望ましいですが、立ちにくければ少しハの字に開いても構いません。
【2.セット】
次に、「セット」と呼ばれる動作に入ります。
セットは射法八節で例えるなら「胴造り」に相当する動作です。
とはいっても、弓道の胴造りほど複雑な動作ではありませんので、初心者でもすぐに馴染めると思います。
スタンスを取った状態のまま、両肩を落として体の重心を低くします。
こうすることで、弓を引くときにも体がブレさせずに、安定した射を行うことができるようになります。
【3.ノッキング】
重心を安定させたら、次に「ノッキング」に入ります。
ノッキングは「矢つがえ」とも訳されますが、射法八節では「弓構え」に相当する行為です。
矢をレストの上に置き、そのままノッキングポイントにはめ込みます。
引き手の人差し指と中指でノックを挟み、人差し指・中指・薬指それぞれの第一関節に弦をかけてください。
あとはグリップを軽く握り、顔を的の方向に向ければOKです。
ただしこのプロセスには個人差があり、人によってやり方が大きく異なります。
そのため、上記のやり方が難しいと感じたら、いろいろ試行錯誤して自分に合った方法を見つけてください。
【4.セットアップ】
ノッキングが完了したら、次に「セットアップ」に入ります。
セットアップは、射法八節でいうところの「打ち起こし」に相当する動作です。
ただし、アーチェリーのセットアップは、そこまで複雑な動作を必要としません。
弓道の打ち起こしのように、細かい角度まで気にしなくてよいので、とりあえず「弓と矢を持って両腕を上げる」ということができていればOKです。
【5.ドローイング】
次はいよいよ弓を引く「ドローイング」に入ります。
ドローイングは、射法八節でいうところの「引き分け」に値するプロセスです。
大雑把に言えば「弓を引きわける動作」なのですが、アーチェリーではこの段階が一番複雑だったりします。
ドローイングはさらに「アンカリング」「ホールディング」「エイミング」などのプロセスに分解されることも多いので、それぞれの動作もしっかり学んでおいたほうがよいでしょう。
【6.フルドロー】
的中率を上げるために、最も重要な動作のひとつが「フルドロー」です。
フルドローは射法八節で言うところの「会」にあたる動作ですね。
要するにフルドローは、引き分けが終わり、狙いを研ぎ澄ませるための行程です。
弓を引き分けてすぐに離してしまうと狙いがブレますが、フルドローで集中力を最大限に高めることで的中率を上げていきます。
考え方は異なりますが、フルドローは海外のアーチャーたちにも重要視されるプロセスです。
【7.リリース】
フルドローで集中力をMAXまで高めたら、いよいよ「リリース」を行います。
リリースは射法八節でいうところの「離れ」に相当する動作です。
ありていに言えば、リリースは「矢を飛ばす動作」のことですね。
フルドローで最大限に溜め込んだ力を解放し、矢を的に向かって飛ばします。
指先に込めた力をどう抜くかが、的中率にも大きく影響してきます。
【8.フォロースルー】
矢を放ったら、最後に「フォロースルー」を行います。
射法八節でいうところの「残身」にあたるプロセスです。
リリースを行った姿勢を、数秒間キープし続けることをフォロースルーといいます。
キープする時間に明確な決まりはありませんが、矢が的の位置に届くくらいまで姿勢を保つのが一般的です。
海外では、フォロースルーはリリースの一部だとされていることもあります。
アーチェリーの射形の解説動画
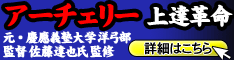
アーチェリー上達革命〜試合でも良い点数を打てるようになる効率的練習法〜【元・慶應義塾大学 洋弓部監督 佐藤達也 監修】DVD2枚組
関連ページ
- アーチェリーで記録を上げるために「視力」は必要不可欠なのか?
- アーチェリーの的は少なくとも18メートル、長ければ70メートルは先に設置されています。サイトやスタビライザーを使うとはいえ、これほど遠方にある的を狙うためには最低限の「視力」が必要になるでしょう。しかし実際のところ、アーチェリーはむしろ「視力が低くてもできるスポーツ」だといえます。アーチェリーで記録を伸ばすために必要なのは、的をしっかりと見据える視力ではなく、スタビライザーやサイトを上手く使いこなして視力を補う「感覚」です。
- アーチェリーの構えアンカリング・ホールディング・エイミングを理解しよう
- 日本で一般的な射法で、スタンス・セット・ノッキング・セットアップ・ドローイング・フルドロー・リリース・フォロースルーの8段階に分割されます。さらに的中率を上げたいならドローイングとフルドローの間に「アンカリング・ホールディング・エイミング」の3つの動作が隠されていることも知っておかなければなりません。そこで今回は、初心者が中級者に上がるために欠かせない「アンカリング・ホールディング・エイミング」の解説をしていきたいと思います。この3種の動作をしっかり理解して、アーチャーとしてひとつ上の段階にレベルアップしていきましょう。
- 弓道経験者がアーチェリーに転向するのは有利?不利?違いは?
- 弓道の選手のなかにはアーチェリーを掛け持ちで行っている選手も少なからず存在します。道具の種類が違うとはいえ、どちらも「弓と矢」を使って行うスポーツですから、確かに両方を掛け持ちするのはそれほど不自然ではないでしょう。両方の競技に共通する動きやコツもあるため、弓道とアーチェリーを掛け持ちすることがプラスに働く可能性も充分に考えられます。そこで今回は、弓道とアーチェリーを掛け持ちすることで発生するメリットとデメリットの両面を徹底的に検証していきたいと思います。